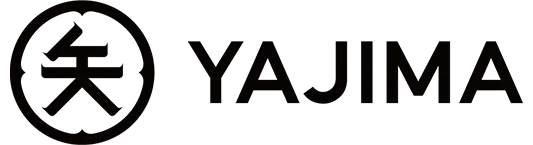賃貸併用住宅の罠を回避するためのポイント|空室対策・自宅の割合など解説

家賃収入をローンの返済に充てることができる賃貸併用住宅が注目を集めていますが、危険だからやめたほうがいい、罠があるといったネガティブな意見を見かけることもあります。
賃貸併用住宅は自宅の延長線でお手軽なイメージもありますが、あくまで賃貸経営であるため失敗のリスクがあるのは事実です。
そこでこの記事では、賃貸併用住宅の罠を回避するために考えるべきポイントを1つずつ解説します。
建築時に考えるべき自宅と賃貸部分の割合、完成後の運用方法や空室対策など、賃貸併用住宅を成功させるために必要な情報をまとめます。
| このコラムのポイント |
|---|
| ・賃貸部分と自宅部分の割合によってメリット・デメリットがあり、どのようなバランスが適しているのか考える必要があります。 ・安定した家賃収入を得るためには、賃貸併用住宅の計画段階で空室対策をすることが大切です。 ・空室発生時のローン返済負担、入居者とのトラブルなど、賃貸併用住宅で考えらえるリスクをチェックしておきましょう。 |
Contents
賃貸併用住宅の罠・リスクとは

賃貸併用住宅は家賃収入でローン返済をまかなえるなどメリットが注目されていますが、注意すべきリスクもあります。
※賃貸併用住宅の罠と言われるリスク
- ・空室が発生するとローン返済の負担が大きい
- ・築年数で賃料相場が下がり収益性が低下
- ・オーナーと入居者の騒音トラブル
- ・家賃滞納や立ち退き拒否
- ・売却が難しくキャピタルゲインは狙いにくい
賃貸併用住宅の罠と言われるリスクは、代表的なものだけでも上記のようにさまざまなパターンがあります。
ただ賃貸併用住宅を建てれば収益が出てローン返済の負担を軽減できるわけではなく、あくまで賃貸経営としてリスクに先回りして対策をする必要があるのです。
例えば、オーナー自身が暮らす賃貸併用住宅で賃貸部分の戸数が少ないと、空室発生時のローン返済の負担は大きくなります。
仮に賃貸部分が一戸の場合、空室期間中は家賃収入がゼロになるため、住宅ローンを全額負担する必要があります。
また、オーナーと入居者が同じ建物で暮らすため、騒音や生活に関するクレームを直接受けやすいなどのデメリットも。
ご自身で暮らす以上、賃貸アパートやマンションのようにキャピタルゲインで初期投資を回収するのも難しいです。
このように、賃貸併用住宅にも注意すべきリスクやデメリットはあるため、事前に把握してしっかり対策することが大切です。
次の章から、賃貸併用住宅の罠を回避し、成功させるためのポイントを1つずつチェックしていきましょう。
賃貸併用住宅の自宅部分の割合の考え方
賃貸併用住宅の自宅部分と賃貸部分の割合は、収益性や資金調達に影響する重要なポイントです。
自宅部分の割合が50%以上、50%未満の場合それぞれのメリット・デメリットを確認して、適切なバランスを考えましょう。
自宅部分の割合が50%以上

賃貸併用住宅の自宅部分の割合が50%以上の場合、次のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | 金利が低い住宅ローンを組める 住宅の規模や初期費用を抑えられる |
| デメリット | 家賃収入が少ない 空室時のリスクが高い |
自宅部分が延床面積の50%以上を占める場合、事業用ローンやアパートローンより金利が低い住宅ローンを組めるのが大きなメリットです。
〈関連コラム〉
賃貸併用住宅に住宅ローンは使える?メリット・デメリットや条件を解説
また、賃貸部分の面積や戸数が少ないため、建物や土地の規模と初期費用を抑えて建てられるのも魅力的。
一方、賃貸部分の戸数を増やせないため家賃収入には上限があり、空室時は無収入の期間が発生するためローン返済が負担になるのがデメリットです。
自宅部分の割合が50%未満

自宅部分より賃貸部分の面積が広い賃貸併用住宅には、次のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | 戸数を増やして家賃収入や利回りを高められる 設計の自由度が高くなる |
| デメリット | 初期費用が高くなる ローンの金利が高い |
賃貸部分の面積と戸数を増やすことで、賃貸物件としての収益性や利回りを高められるのは大きなメリットです。
立地が良く賃貸需要が高いエリアで賃貸併用住宅を建てるなら、賃貸部分を広くして収益性を高めた方がローン返済の負担を軽減できる可能性があります。
また、面積に余裕が出ることで設計の自由度が高くなり、さまざまな賃貸ニーズに対応しやすいのも強みです。
例えば、ファミリー層が多いエリアなら部屋数を増やしたり、競合より広めの部屋や充実した設備で入居率や賃料設定を高めたりする考え方もあります。
一方、賃貸部分の面積が広くなることで、土地取得費用や建築費用が多めにかかり、資金調達のハードルが高くなるのは注意すべきリスクです。
また、自宅部分の面積が50%未満だと住宅ローンを組めないケースが多く、金利が高い事業用ローンやアパートローンを組むことになるのもデメリットといえます。
賃貸併用住宅の空室対策の考え方

どのような規模の賃貸併用住宅を建てる場合でも、空室対策は重要です。
新築物件は入居者を見つけやすい傾向があるものの、建てる前にしっかり空室対策して罠やリスクを回避しましょう。
建てる前に立地を確認
具体的な間取りやプランを考える前に、まずは賃貸併用住宅を建てる場所の賃貸需要や土地の周辺環境を確認しましょう。
そもそも賃貸需要や家賃相場が低いエリアだと、空室対策をしても効果が出ず、思ったような家賃収入を得られない可能性があります。
相続した土地や建て替えなどで賃貸併用住宅を検討する場合は、近隣にどのような賃貸物件があり、どれくらいの家賃相場なのか調査しましょう。
これから土地を購入して賃貸併用住宅を建てる場合は、ご自宅としての住環境と賃貸需要のバランスを考えることが大切です。
また、日当たりや騒音など、賃貸物件を探す人が重視するポイントも確認する必要があります。
立地や周辺環境は入居率に直結する重要な要素ですから、計画を進める前にしっかりチェックしましょう。
ニーズに合わせた間取りと環境づくり
具体的に賃貸併用住宅の間取りやデザインを考える際は、地域の賃貸ニーズをしっかり調査して暮らしやすい環境をととのえることが空室対策につながります。
例えば、学生や新卒の単身者とファミリーでは、賃貸部分に必要な部屋数や延床面積、キッチンやユニットバスなどの設備も変わってきます。
また、単身女性の賃貸需要が高いエリアなら、プライバシー保護やセキュリティ観点の工夫をした方が、入居率で有利です。
地域性や公共交通機関との位置関係も踏まえて、駐車場や駐輪場の必要性も考える必要があります。
賃貸物件を探すユーザー目線になり、暮らしやすいと思える間取りや環境をつくりましょう。
競合物件との差別化
近隣の競合物件を調査して差別化を図ることも、賃貸併用住宅の空室対策の1つです。
最近は不在中も宅配便を受け取れる宅配ボックス、インターネット環境やフリーWi-Fi付きなど、人気の高い設備で空室対策するケースも増えています。
また、近隣にペット可物件が少ないなら、取り入れてみるのも1つのアイデアです。
間取りや内装に工夫して、デザイナーズ賃貸物件として売り出し、入居率や賃料を高めるのも効果的な方法です。
想定する入居者に合わせてトレンドのアイデアを取り入れ、「ここに住みたい」と思ってもらえるように競合と差別化を図りましょう。
賃料設定
入居率と家賃収入に影響する賃料設定も、賃貸併用住宅でしっかり考えるべきポイントです。
賃貸併用住宅の賃料設定は積算法・収益分岐法などさまざまな方法がありますが、近隣の似ている物件と比較する賃貸事例比較法がスタンダードです。
※賃貸事例比較法の項目
- ・立地(駅からの距離)
- ・築年数
- ・建物構造
- ・間取りや面積
- ・設備
賃貸事例比較法は、上記の条件が似ている物件を調査し、適切な賃料を求める方法です。
家賃収入を考えると賃料はなるべく高くしたいところですが、相場とかけ離れると空室リスクが増加します。
前述したほかの対策も加味しつつ、家賃収入と入居率のバランスを取れる賃料を設定しましょう。
また、築年数が経つと賃料相場は低下していきますので、将来的な家賃収入も踏まえて資金計画を立てることが大切です。
賃貸併用住宅の資金計画の考え方

賃貸併用住宅は一般的な注文住宅の資金計画にくわえて、賃貸物件としての経営計画も加味して考える必要があります。
例えば、賃貸部分が一戸の場合空室期間中は家賃収入がゼロになるため、ローン返済はすべて自己負担になります。
満室想定で資金計画を立ててしまうと、空室の発生や築年数の経過による賃料の低下などで、ローン返済が苦しくなってしまうリスクも。
また、退去時の原状回復工事費用、外壁塗装などのメンテナンス費用も、運転資金として確保しておく必要があります。
一般住宅のようにご自身の年収とローン返済額のバランスを考えるだけでなく、さまざまな要素について考える必要があるのです。
また、次の章で解説する運用方法によっても、ランニングコストは変わってきます。
賃貸併用住宅の運用の考え方

賃貸併用住宅の計画時は、完成した後の運用方法まで考えることが大切です。
主な運用方法は次の3パターンです。
※賃貸併用住宅の運用方法
- ・オーナーの自主管理
- ・委託管理
- ・サブリース
賃貸部分が自宅と隣接しているためオーナー自身で管理しやすいですが、どのような管理業務があり、とこまで自分でやるのか事前に把握する必要があります。
また、費用は抑えられるものの手間がかかり、入居者対応や新規募集、原状回復の手配なども自分でこなすためハードルは高めです。
管理会社に委託する場合は、ほとんどの業務を任せることができますが、契約内容によって費用が変わります。
オーナー自身の手間はかかりませんが、管理費用がかかるため、家賃収入とローン返済を踏まえて前述した資金計画を立てる必要があります。
サブリースは管理会社と転貸借契約を結び、賃貸部分の運用をすべて任せる方法です。
一般的に家賃保証があるのは大きな魅力ですが、管理料が高額になるため収益性は低くなります。
このように、どの運用方法にもメリット・デメリットがあるため、賃貸併用住宅の間取りや収益性を踏まえて、適切な選択をしましょう。
まとめ
賃貸併用住宅にはメリットもありますが、あくまで賃貸経営であるため、注意すべきリスクもあります。
完成後に失敗に気づき後悔しないように、計画段階でリスクに対処し、安定した経営を目指しましょう。
賃貸併用住宅で注意すべきポイントは多いため、施工実績が豊富な会社に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。
矢島建設工業は、多くの賃貸併用住宅づくりをお手伝いした実績をもとに、お客様に合わせたプランのご提案をいたします。
賃貸併用住宅のことなら、土地探し・間取りづくり・資金計画など、どんなこともお気軽にご相談ください。



監修者情報

-
矢島建設工業株式会社 商環境事業部 事業部長
一級建築施工管理技士/監理技術者/サウナ・スパプロフェッショナル/DIYアドバイザー -
北海道生まれ。乃村工藝社、日商インターライフ、秀建などを経て2024年矢島建設工業に入社。
1985年から様々な商業施設の設計施工業務に携わり、3000件を超えるリアル店舗の設計・監修や施工・マネジメントを手掛ける。
近年はサウナ・温浴施設のプロジェクトに関わり、サウナ事業を学ぶため全国のサウナやフィンランド・ドイツ・エストニアにも渡って知見を広めている。
新事業のアドバイスを、ものづくりの目線から忌憚のない意見をする事がモットー。
第2期サウナ開業塾生
第1回Tehdään Sauna! Finland 修了
最新の投稿
- 2025年4月1日二世帯住宅2025年建築基準法改正で二世帯住宅はどう変わる?費用や工期など影響について解説
- 2025年3月31日リフォーム外壁カバー工法の失敗・後悔例|解決方法「モルタルカバー工法」も紹介
- 2025年3月7日平屋平屋が人気なのはなぜ?ブームの理由やトレンドの間取りの傾向を解説
- 2025年2月27日注文住宅ハウスメーカーと工務店の違いは?価格差だけでなくコストパフォーマンスを比較しよう