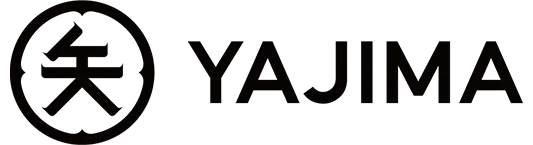二世帯住宅はデメリットだらけ?やめた方がいいと言われる理由と対策

二世帯住宅について情報収集していると、「デメリットだらけ」「やめた方がいい」などネガティブな意見が目立ちますよね。
確かに、年代が異なる2つの家族が暮らす住まいづくりは、一般的な核家族向けの住宅より難易度は高いです。
しかし、デメリットを知っていれば対策することは可能で、家事や育児の分担、節税効果などのメリットもあります。
そこでこの記事では、二世帯住宅のデメリットを1つずつピックアップして、対策とセットで分かりやすく解説します。
暮らしやすい二世帯住宅づくりのために、ぜひお役立てください。
| このコラムのポイント |
|---|
| ・生活リズムのズレやプライバシー性の低さなど、二世帯住宅のデメリットを把握して対策することが大切です。 ・家事や育児の分担、相続税の節税など、二世帯住宅ならではのメリットもたくさんあります。 ・二世帯住宅の失敗や後悔を防ぐには、親子間でしっかり話し合い、実績が豊富な施工会社のサポートを受けるのがおすすめです。 |
二世帯住宅はデメリットだらけって本当?

昔の日本は親子二世帯で一緒に暮らすのが一般的でしたが、核家族化が進み二世帯住宅に対してネガティブなイメージが強くなっています。
特に、近年はライフスタイルが大きく変化しているため、同じ家で暮らすと親子世代間の価値観のギャップが問題になるケースはあります。
また、家族とはいえ、離れて暮らしているうちに生活に対する考え方が変わり、再び一緒に暮らすとズレが気になる可能性も。
しかし、二世帯住宅のデメリットを正しく把握していれば、対策することは可能です。
また、二世帯住宅にはデメリットだけでなくメリットもありますので、別々に家を建てるよりコストを抑えて暮らしやすいマイホームも実現できます。
二世帯住宅の失敗を防いで暮らしやすいマイホームに仕上げるために、デメリット・メリット両面を1つずつチェックしていきましょう。
二世帯住宅はやめた方がいいと言われる理由

まずは二世帯住宅のデメリットについて、「やめた方がいい」「失敗した」と言われることが多いケースをピックアップしてみましょう。
対策については後半で解説しますので、まずはデメリットをしっかり覚えておいてください。
プランづくりが難しい
二世帯住宅は一般的な住まいづくりより考えるべきことが多く、プランづくりが難しいのがデメリットと言われています。
玄関や水回り設備の共有・分離、それぞれの世帯の距離感など、二世帯住宅ならではの選択肢があり、意見が食い違うことも少なくありません。
親子で気兼ねして意見をはっきり伝えられず、実際に暮らし始めてから失敗に気づくケースもあるようです。
どのような間取りがマッチするかは家族によって変わるため、ほかの二世帯住宅の成功例をそのまま真似できないのも難しいポイントです。
生活リズムや習慣のズレによるストレス
リビングや玄関などを共有する二世帯住宅の間取りの場合、親子間の生活リズムや習慣のズレによるストレスを感じることも多いようです。
例えば、就寝や起床時間が違うと、物音で目を覚ましたりテレビや話し声で寝付けなかったりしてストレスの原因になります。
また、食事や入浴なども、時間帯がずれると生活のストレスにつながる可能性があります。
プライバシー性が低く気を使う
二世帯住宅や親子間でコミュニケーションを取りやすい反面、プライバシー性が低くなるのもデメリットに挙げられることが多いポイントです。
同じ建物で暮らすとどうしてもお互いの行動が見えてしまうため、気を使ってしまいのびのび暮らせないケースがあります。
建築費用が高額になり費用負担で揉めやすい
二世帯住宅は3~4人家族の平均的な注文住宅より延床面積が広いため、建築費用が高額になり、費用の負担や住宅ローンの組み方で意見がまとまらないケースもあります。
親子どちらが頭金を出すのか、住宅ローンを誰が返済するのかなど、選択肢が多い分うまく決められないリスクがあるのです。
仮に親子どちらかが多く費用を負担する場合、気兼ねしてプランについて意見を言いづらくなるケースもあるようです。
また、親子ペアローン、リレーローンなど住宅ローンを組む方法も複数あり、万が一親が亡くなったときのことまで考える必要があります。
ランニングコストが高額になる
部屋数が多く延床面積も広くなる二世帯住宅は、光熱費や将来のリフォーム費用、固定資産税などのランニングコストが高額になるのも注意すべきデメリットです。
エアコンや給湯器の数が増えると、毎月の光熱費は一般的な広さの住宅より高くなります。
親子世帯で光熱費を上手く分担すれば負担を軽減できますが、実際に暮らしてみて思ったより高くなり、トラブルになるリスクもあります。
外壁や屋根の塗装、固定資産税なども、建物や土地の大きさに応じて高くなるため、負担割合や金額について揉める可能性も。
売却難易度が高い
将来何らかの理由で住み替えが必要になった際、一般的な住宅より売却難易度が高いのも二世帯住宅のデメリットです。
二世帯住宅は家族の人数やライフスタイルに合わせてオーダーメイドで決めるため、ほかの人にとって住みやすいとは限らず、買い手を見つけにくい傾向があります。
相続トラブルになりやすい
親世帯が他界した際、ほかの兄弟がいる場合に相続トラブルのリスクがあるのも、二世帯住宅はやめた方がいいと言われる理由の1つです。
二世帯住宅は法定相続分に応じて現物で分割ができないため、誰が相続するのかでトラブルになりやすいのです。
また、共有名義で相続する方法もありますが、運用方法や売却に全員の同意が必要になるため、意見がまとまらずトラブルになるリスクもあります。
二世帯住宅にはメリットもある

先ほど挙げたようなデメリットだけでなく、二世帯住宅にはさまざまなメリットもあります。
デメリットに対策すればメリットを活かした二世帯住宅を建てることもできますので、先にチェックしておきましょう。
家事・育児を分担できる
親世帯が家事や育児に参加することで、子世帯の負担を軽減できるのは二世帯住宅の大きなメリットです。
特に子世帯が共働きの場合、日中に両親にお子さまを見てもらえるのは大きな負担軽減になりますね。
親世帯にとっても、身近で孫の成長を感じられることはメリットと言えるでしょう。
誰かしら在宅する時間が多く防犯面で有利
家族の人数が多く、誰もいない時間が少ないため、空き巣などのリスクを軽減できるのも二世帯住宅ならではのメリットです。
完全分離型の間取りでも、同じ建物内に人が居て出入りもあるので、空き巣に狙われるリスクを軽減できます。
両親が近くに居るので介護などサポートしやすい
将来両親の介護が必要になった際も、二世帯住宅で同居していればサポートしやすいのもメリットの1つです。
両親が遠方に住んでいる場合、介護サービスを探したり、通ってサポートをしたりするのは大きな負担になります。
一緒に住んでいれば体調の変化などにも素早く気づけますし、親子どちらにとても安心感がありますね。
相続税の節税になる
二世帯住宅は「小規模宅地等の特例」を適用して、相続税の負担を減らせる可能性があります。
具体的には、親子で同じ敷地内(330㎡以下)に同居して生計を共にしている場合、相続時に土地の評価額を最大80%減額できます。
土地の資産価値が高いと相続税も高額になるため、負担を軽減するメリットも大きいです。
補助金の対象になることも
自治体によっては、Uターン移住で地元にいる親と同居する場合、住宅取得費用に対する補助金制度を用意していることもあります。
また、親子で資金を出し合って省エネ性能や耐久性が高い二世帯住宅を建てれば、国の補助金要件を満たして費用負担を軽減できる可能性も。
二世帯住宅の失敗を防ぐ対策

ここまで紹介したデメリットに対策して、二世帯住宅のメリットを高めるために、次のような取り組み方をしましょう。
まずはライフスタイルについて話し合う
具体的なプランを考える前に、まずは親子間で話し合いの時間を設けて、お互いの現在のライフスタイルと理想を確認しましょう。
起床・就寝・食事・入浴など、生活サイクルを細かく確認することで、間取りの失敗や後悔を防ぎやすくなります。
また、親世帯がどれくらい子育てに参加したいのか、お互いにどれくらいプライベートな時間が欲しいのかなど、気兼ねせずしっかり意見を伝えることが大切です。
共有スペースについて考える
二世帯住宅づくりでは、前述したライフスタイルを踏まえて、どの間取りを共有・分離するのか考えることも大切です。
※二世帯住宅の間取りパターン
- 完全分離型
- 完全共有型
- 部分共有型
例えば、生活時間帯のズレが大きくプライバシーを重視するなら、共有スペースのない完全分離型の間取りが向いています。
一方、ある程度コミュニケーションや家事・育児の連携を取るなら、完全共有型・部分共有型でバランスを取るのも1つの考え方。
それぞれの間取りパターンの特徴や考え方、間取り実例をこちらのコラムで紹介しています。
〈関連コラム〉
完済までの資金計画を立てる
二世帯住宅の資金計画を立てる際は、完済までのことをなるべく細かくシミュレーションしましょう。
例えば、親子ペアローンを組む場合は、親世帯がいつまで働くのか、亡くなった場合にどうなるのかなど、事前に考えておく必要があります。
また、将来介護が必要になったときの出費なども見据えて、無理のない資金計画を立てるのも大切なポイントです。
暮らしのルールを事前に定める
間取りのことだけでなく、実際に暮らし始めてからのことも細かくルールを決めておくことが大切です。
※二世帯住宅の暮らしのルールの例
- 食事や入浴の時間や順番
- ゴミ出しの担当
- 休日の過ごし方
- 友人を招いたときの過ごし方
- 光熱費や固定資産税の負担割合
上記はあくまで一例で、すべてのことをきっちり決めておく必要はありません。
お互いに気になるポイントを事前に取り決め、暮らし始めてから気づいたことはその都度相談することを確認しておけば生活のストレスを防止できます。
兄弟も含めて相続・介護について事前に話し合う
親世帯の介護が必要になったときや、相続時のことについて兄弟を含めて相談しておくのも大切なポイントです。
例えば、一緒に住んでいる子世帯だけでなく、兄弟も介護をサポートできるのか、施設に入る場合の費用を一緒に負担できるのかなど、事前に相談しておくとトラブルを回避しやすくなります。
また、親が亡くなったときに二世帯住宅を誰が相続するのか決めておき、遺言状を残しておくと遺産分割協議のトラブルを防ぐことができます。
相続や介護やご家族全員にとって重要なことですから、二世帯住宅の計画をきっかけにしっかり話し合っておきましょう。
まとめ
二世帯住宅にはデメリットもありますが、事前に課題を把握して対策すれば、メリットを活かして理想のマイホームを建てることが可能となります。
ただし、一般的な注文住宅より考えるべきポイントは多いため、二世帯住宅の実績が多い設計施工会社のアドバイスやサポートを受けることがとても大切です。

東京・神奈川・千葉・埼玉で二世帯住宅をご検討の際は、矢島建設工業にご相談ください。
これまで多くの二世帯住宅づくりをサポートしてきた実績がございますので、ご家族の意見をお伺いし、暮らしやすいプランをご提案いたします。



監修者情報

-
矢島建設工業株式会社 商環境事業部 事業部長
一級建築施工管理技士/監理技術者/サウナ・スパプロフェッショナル/DIYアドバイザー -
北海道生まれ。乃村工藝社、日商インターライフ、秀建などを経て2024年矢島建設工業に入社。
1985年から様々な商業施設の設計施工業務に携わり、3000件を超えるリアル店舗の設計・監修や施工・マネジメントを手掛ける。
近年はサウナ・温浴施設のプロジェクトに関わり、サウナ事業を学ぶため全国のサウナやフィンランド・ドイツ・エストニアにも渡って知見を広めている。
新事業のアドバイスを、ものづくりの目線から忌憚のない意見をする事がモットー。
第2期サウナ開業塾生
第1回Tehdään Sauna! Finland 修了
最新の投稿
- 2025年4月1日二世帯住宅2025年建築基準法改正で二世帯住宅はどう変わる?費用や工期など影響について解説
- 2025年3月31日リフォーム外壁カバー工法の失敗・後悔例|解決方法「モルタルカバー工法」も紹介
- 2025年3月7日平屋平屋が人気なのはなぜ?ブームの理由やトレンドの間取りの傾向を解説
- 2025年2月27日注文住宅ハウスメーカーと工務店の違いは?価格差だけでなくコストパフォーマンスを比較しよう