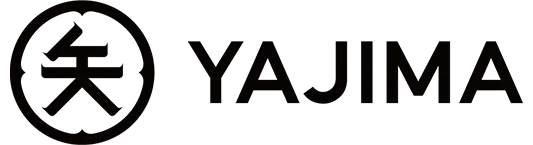二世帯住宅の賢い建て方|将来を見据えた設計や補助金活用・住宅ローンの組み方を解説

親子で一緒に暮らす二世帯住宅はメリットも多いものの、間取り設計や資金計画など難しいポイントが多いと感じる方も多いようです。
また、建てた直後のことだけでなく、ライフスタイルの変化や親世帯が暮らさなくなった後のことも見据えて設計しないと、ムダが発生して持て余してしまうケースも。
そこでこの記事では、二世帯住宅を建てる前に覚えておくべき、賢い建て方のポイントを詳しく解説します。
間取りの基本的な考え方、将来を見据えた運用方法、資金計画や補助金活用など、二世帯住宅を建てるときに把握すべき情報を網羅します。
どのような間取り・ライフスタイルの二世帯住宅にも当てはまる基本的な考え方を解説しますので、ぜひ理想の住まいづくりにお役立てください。
| このコラムのポイント |
|---|
| ・二世帯住宅はそれぞれの世帯がストレスなく生活でき、将来もムダなく運用できるように間取りを考えることが大切です。 ・親世帯のスペースが空いた場合を想定して、リフォーム・賃貸併用住宅への転用なども検討しておきましょう。 ・親子の資金配分や住宅ローンの組み方、補助金の活用など、お金に関する賢い建て方も解説します。 |
Contents
二世帯住宅は失敗が多い?

二世帯住宅について調べるとデメリットや失敗談が目に付き、「後悔する」「やめたほうがいい」といった意見も少なくありません。
しかし、これだけ多くの失敗談があり注意喚起されていても、実際に完成して暮らし始めてから後悔するケースもあります。
親子間の意見の食い違いやストレスから、完成して数年で売りに出されたり、どちらかの世帯が家を出てしまったりする失敗例も。
また、親世帯の介護施設への入居などでスペースを持て余したり、住宅ローンの支払いが苦しくなったりするケースもあります。
二世帯住宅づくりの失敗や後悔を防ぐためには、親子世帯で長く快適に暮らすための設計、無理のない資金計画、将来の活用方法など、さまざまなポイントに配慮することが大切です。
こちらのコラムで二世帯住宅の代表的なデメリットや、やめた方がいいと言われるポイントへの対策について詳しく解説しています。
〈関連コラム〉
二世帯住宅はデメリットだらけ?やめた方がいいと言われる理由と対策
二世帯住宅の間取りの基本的な考え方

親世帯・子世帯が暮らす二世帯住宅では、それぞれが快適かつスムーズに暮らせる間取りを考えることが重要です。
※二世帯住宅の間取りパターン
- 完全分離型
- 完全共有型
- 部分共有型
二世帯住宅は大きく分けると上記の3パターンがありますが、どの間取りを共有・分離するのがベストかは、家族によって異なります。
ほかの家の間取りをそのまま取り入れるのではなく、二世帯間の意見をすり合わせて失敗やムダを無くすことが大切になります。
例えば、部分共有型の間取りでリビングや水回りを2つに分けても、玄関が1つだと結局プライバシー性などの点でストレスを感じることも多いです。
また、それぞれの生活スペースを分けても、間取りがつながっていて干渉できるようになっていると、快適に暮らせない可能性も考えられます。
しかし、部分共有型や完全分離型の間取りでは、本来1つで済む部屋や設備を2つつくるために、敷地面積や費用が多めにかかります。
二世帯間のライフスタイルや意見がマッチしているなら、生活スペースを共有した方が、費用を抑えて暮らしやすい間取りになる可能性もあるのです。
二世帯住宅の間取りを考える際は、費用とライフスタイルのバランスを取り、家族全員が快適に長く暮らせる間取りをつくるのが基本的な考え方です。
こちらのコラムで二世帯住宅の間取り実例や考え方をさらに詳しく解説していますので、参考にしてください。
〈関連コラム〉
二世帯住宅の将来を見据えた建て方のポイント
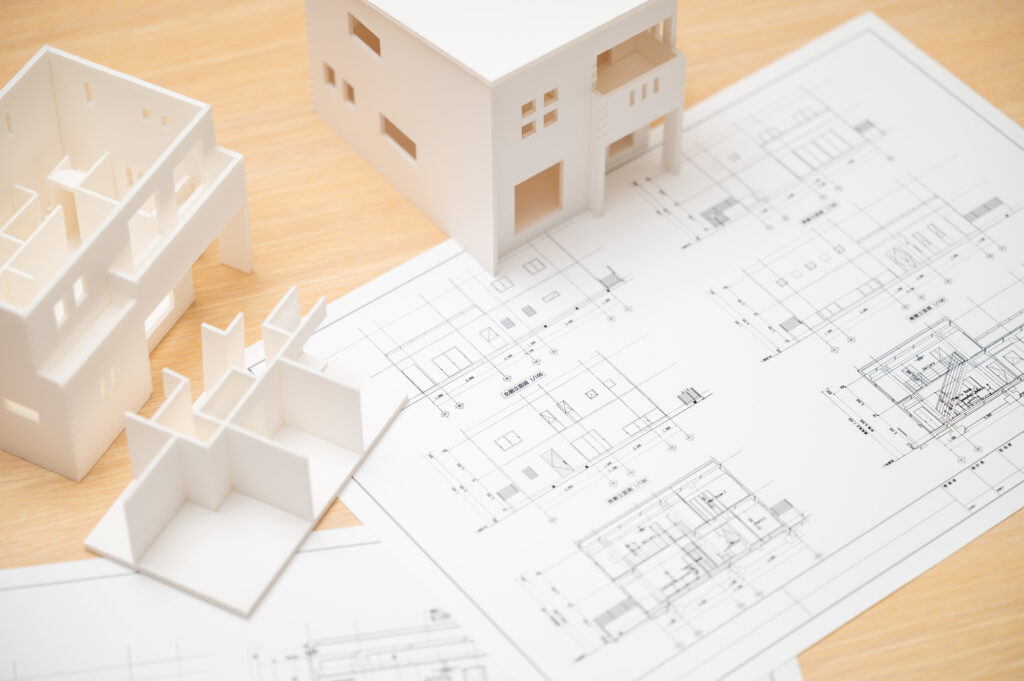
二世帯住宅は完成した直後のことだけでなく、家族構成やライフスタイルの変化といった将来のことまで見据えて建てることが大切です。
将来親が亡くなった後、親世帯のスペースをそのままにしておくのはもったいないですし、掃除やリフォーム、固定資産税など2世帯分の負担も厳しくなります。
また、二世帯住宅は売却難易度が高く、ライフスタイルが変わってもすぐに住み替えするのは難しい傾向があります。
親世帯のスペースが空いたときを想定して、リフォームで広く暮らせるようにしたり、賃貸運用して家賃収入を得たり、運用方法を考えておくことが重要です。
例えば、玄関が2つある完全分離型の間取りなら、親世帯のスペースを賃貸にして家賃収入を得ることが可能です。
しかし、賃貸併用住宅に転用することを想定して間取りを考えておかないと、音やプライバシーなどの問題で入居者がうまく決まらない、クレームが入るといったリスクが考えられます。
〈関連コラム〉
賃貸併用住宅の罠を回避するためのポイント|空室対策・自宅の割合など解説
リフォームして自分たちで活用するのか、賃貸化するのか、売却するのかなど、将来の運用方法を想定して、適切な間取り設計や建て方に工夫をしてみましょう。
二世帯住宅の資金計画やローンの組み方のポイント

二世帯住宅は一般的な注文住宅より土地取得費用・建築費用が高額になるため、資金計画や住宅ローンの組み方も建てるときのポイントになります。
親世帯・子世帯どちらがどれくらい資金を出すのか、収入や支出だけでなく、将来のライフイベントまで踏まえて、完済までの計画を立てる必要があるのです。
例えば、親子両方で費用を負担する場合、住宅ローンの組み方も複数パターンあります。
| 収入合算 | 親子・夫婦の収入を合わせて1つの住宅ローンを組む |
| 親子ペアローン | 親世帯・子世帯それぞれで住宅ローンを返済する |
| 親子リレーローン | 前半は親世帯がローンを返済し、途中で子世帯が引き継ぐ |
親世帯・子世帯の収入が比較的高い場合は、収入合算で短期間の住宅ローンを組めば利息支払いを抑えられる可能性があります。
しかし、収入合算では親が死亡しても住宅ローンの残債は免除されないため、子世帯の負担が大きくなってしまうリスクがあります。
子世帯が若く年収がこれから増えそうなケースでは、親子リレーローンで前半は親が返済を負担し、途中でバトンタッチするのも1つの考え方です。
それぞれメリット・デメリットがあるため、二世帯でしっかり話し合い、完済までの無理のない計画を立てることが大切です。
二世帯住宅は補助金を活用して負担を抑えよう

二世帯住宅を賢く建てるためには、国や自治体の補助金を活用して費用負担を抑えるのもポイントです。
例えば、2025年度の「子育てグリーン住宅支援事業」は二世帯住宅でも活用でき、住宅性能を高めた「GX志向型住宅」の水準を満たせば1戸当たり160万円の補助金を受けることができます。
二世帯住宅は光熱費も多くかかるため、省エネ性能を高めることによる節約効果も期待でき一石二鳥ですね。
また、二世帯住宅を建てる自治体によっては、独自の補助金を用意していることもあります。
| 自治体/制度 | 主な要件 |
| 神奈川県厚木市/親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金 | 親世帯と近居・同居のため市外から転入する子世帯に対し補助金を支給。 新築同居の場合は60万円。(条件により加算額あり) |
| 東京都台東区/三世代住宅助成 | 区内の指定地域で親・子・孫の三世帯が同居する一戸建て住宅の建築に対し、120万円の助成金を支給。 |
※詳しくは各自治体のHPなどで情報を確認してください。
上記は一例ですが、指定された自治体の区域で一定の要件を満たす二世帯住宅を建てれば、補助金を受け取れる可能性があります。
補助金の要件や金額はさまざまなので、二世帯住宅を建てる自治体の制度をチェックしてみましょう。
まとめ
二世帯住宅を建てるときは、間取り・将来の運用方法・資金計画などさまざまなポイントへの配慮が必要です。
二世帯住宅は、実際に暮らし始めてから失敗に気づき後悔しても対処するのが難しいです。
失敗や後悔しやすいポイントを事前に把握し、しっかり対策して暮らしやすい二世帯住宅を建てましょう。
また、二世帯住宅づくりの実績が豊富な施工会社に相談して、適切なアドバイスを受けるのも失敗を防ぐポイントです。
二世帯住宅づくりのことなら、神奈川県横浜市の矢島建設工業にご相談ください。
これまで多くの二世帯住宅づくりで培ってきたノウハウを活かし、お客様のライフスタイルをお伺いしたうえで理想的なプランをご提案いたします。



監修者情報

-
矢島建設工業株式会社 商環境事業部 事業部長
一級建築施工管理技士/監理技術者/サウナ・スパプロフェッショナル/DIYアドバイザー -
北海道生まれ。乃村工藝社、日商インターライフ、秀建などを経て2024年矢島建設工業に入社。
1985年から様々な商業施設の設計施工業務に携わり、3000件を超えるリアル店舗の設計・監修や施工・マネジメントを手掛ける。
近年はサウナ・温浴施設のプロジェクトに関わり、サウナ事業を学ぶため全国のサウナやフィンランド・ドイツ・エストニアにも渡って知見を広めている。
新事業のアドバイスを、ものづくりの目線から忌憚のない意見をする事がモットー。
第2期サウナ開業塾生
第1回Tehdään Sauna! Finland 修了
最新の投稿
- 2025年4月1日二世帯住宅2025年建築基準法改正で二世帯住宅はどう変わる?費用や工期など影響について解説
- 2025年3月31日リフォーム外壁カバー工法の失敗・後悔例|解決方法「モルタルカバー工法」も紹介
- 2025年3月7日平屋平屋が人気なのはなぜ?ブームの理由やトレンドの間取りの傾向を解説
- 2025年2月27日注文住宅ハウスメーカーと工務店の違いは?価格差だけでなくコストパフォーマンスを比較しよう