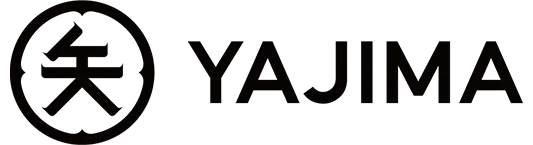2店舗目のサウナづくりで考えるべきこと|業界の動向や課題も解説

相変わらず活況なサウナ業界では、1店舗目の経営が軌道に乗り、2店舗目の出店を検討している方も少なくありません。
しかし、サウナの需要が今後どうなるのか、2店舗目をどのようなコンセプトにするべきなのかなど、気になるポイントも多いですよね。
そこでこの記事では、2店舗目のサウナ出店計画において考えるべきことや、クリアすべき課題について解説します。
| このコラムのポイント |
|---|
| ・サウナブームは沈静化したという意見もありますが、郊外の大型店舗の出店なども増えており、新しいステージに移行した感があります。 ・新しいサウナ施設やサービスが増えたことで、サウナユーザーの店舗選びの精度や口コミの重要性がよりまっています。 ・2店舗目のサウナづくりでは、ただ競合と差別化をするだけでなく、設備やサービス内容を含めて基本的な部分のクオリティを高める機会となります。 |
Contents
2店舗目のサウナ出店のチャンスは?

2019年のドラマをきっかけとした第三次サウナブームは沈静化し、文化として定着したという意見もありますが、まだまだ新規出店も続いています。
しかし、東京などの都市部では新規出店が続いたことで競争が激化し、不採算の店舗も増えだしており、1店舗目を出店した頃よりもユーザーの思考や傾向も変わってきたと考えるべき状況です。
最近はヘビーユーザーだけでなく一般層のライトユーザーが増えだしたことで、郊外の大型店舗の新規出店もその思考が目立ちます。
ファミリーやカップルなどで大型店舗を訪れ、食事やチルアウトなどのサービスも含めて時間浪費型として楽しむ傾向が見受けられます。
このように、エリアやターゲットモデルを明確にすることが2店舗目を開業するチャンスとなるでしょう。
しかし、2店舗目を開業する前に考えるべき課題もあります。
サウナブームで見えてきた課題の傾向とは?

サウナブームが続いて多くの店舗やサービスが登場したことで、データが蓄積し見えてきた課題もあります。
多くのサウナ施設を比較検討できるようになったことでユーザーの目が肥え、施設やサービスに求められるクオリティは高くなっています。
オープン直後は注目を集めてにぎわっていても、サウナ自体のつくりやクオリティ、サービスの提供が追い付かないと、悪い口コミが付いてしまうケースも少なくありません。
例えば、デザインやコンセプトが魅力的なサウナ室をつくっても、温度が低い・マット交換がない・かび臭い・スタッフの対応が遅いなど、そもそものクオリティが低いとユーザーは満足してくれません。
最近は口コミでサウナ施設を選ぶユーザーも多く、悪い評判が多くなると新規顧客の集客力やリピーター率の低下を招く恐れもあります。
また、最近は基本の温浴ゾーンと、より多くのサウナを楽しめるオプションゾーンを分ける施設も増えていますが、料金体系や利用方法が分かりにくいケースも。
店舗レイアウトが分かりにくかったり、従業員のサービスや対応力が不足したりすると、ユーザーが不安や不満を覚え、評価が低下するリスクがあります。
かつての岩盤浴のように、1つのマイナスな話題がきっかけでブームが終わるケースもあり、サウナも例外ではありません。
サウナブームから続く追い風の状況をキープし、さらに文化として日本に根付かせていくには、業界全体で丁寧な店舗・サービス作りに取り組むことが必要です。
2店舗目のサウナ開業で考えるべきポイント

2店舗目のサウナづくりでは、ただトレンドを取り入れて競合と差別化するだけでなく、1店舗目で培ったノウハウや気づきを含めて、ユーザーにとって本当に魅力的な施設とサービスをつくることをオーナーは目指しています。
顧客感動満足・従業員満足・より良い仕組み・人財をマネジメントする、2店舗目のサウナ開業で考えるべきポイントは多岐にわたるでしょう。
サウナ自体のクオリティ
大前提として、サウナ室や水風呂、ととのいスペースを含めた施設全体のクオリティを担保することが先ずは大切です。
今までにないコンセプトの目新しいサウナをつくっても、本来の機能性が不足しては本末転倒です。ロッカーの数=最大収容人数から、洗い場・サウナ室・温風呂・水風呂・ととのいスペースの収容人員スペースを検証します。それぞれの滞在時間がポイント。
温度が低く身体が十分に暖まらない、ストーブなどの設備が壊れたときのバックアップを考慮できていない、清掃しにくい造りで不衛生な状態、リネンの負担など、マイナス面はユーザーの満足度に直結します。
ただ集客力が高いサウナをつくるだけでなく、本来の機能性や安全性も考慮して、ユーザー目線で気持ち良く利用できる施設づくりを心がけましょう。
サウナ以外も含めた施設づくり
サウナを出た後の美味しい食事、心置きなくリラックスできる休憩スペースなど、施設全体のトータルコーディネートも重要です。
前述したように近年はサウナだけに入りにくるヘビーユーザーだけでなく、家族や友人と長時間施設で過ごすニーズも増加しています。
サウナ自体のクオリティが高くても、食事が粗末だったり、ととのった後の時間を過ごせるスペースが無かったりすると、悪い口コミが付く可能性もあります。
こちらのコラムでサウナ施設のトレンドについて解説していますので、あわせてご覧ください。
〈関連コラム〉
現代サウナ施設のトレンドデザイン:癒しと革新の融合/最新店舗紹介も
分かりやすいサービスや料金体系
ユーザーの目線に立ち、初めて利用する方でも分かりやすいサービス内容や料金体系を設定することも重要なポイントです。
最近は温浴部分と、サウナ・岩盤浴部分を分けるような料金体形も多いですが、ユーザーにとって分かりにくくなっているケースも少なくありません。
基本料金でどこまで利用できるのか、追加料金がいくらかかり何ができるようになるのかなど、なるべくサービス内容や料金体系をシンプルに提示するのが望ましいです。
また、基本料金と追加料金のゾーンを分ける場合、ユーザーニーズに寄り添う施設づくりも求められます。
例えば、追加料金ゾーンにクオリティの高いサウナと水風呂はあるものの、温かい浴槽は基本料金の温浴ゾーンにしかない場合、わざわざ着替えて移動する手間がありユーザーの利便性は低下します。
多様なユーザーニーズに応えられるためのサービス内容や施設のレイアウトは、まるでパズルのように難題ですが、集客力アップのために取り組むべき課題でしょう。
ランニングコスト
1店舗目の経営で、ランニングコストを削減することがいかに重要かを理解した方は少なくないでしょう。
2店舗目のサウナづくりでは、光熱費や人件費、メンテナンスなどさまざまな視点でランニングストを削減する方法を検証する必要があります。
井戸水と浄化槽のセットで上下水道代を減らす、割高な電気をガスに変えてみる、節水できる給水設備を採用するなど、水光熱費を下げる工夫はさまざまです。
また、消耗しやすい造作部分の営繕簡素化、ワンオペを可能とするゾーニングなど、メンテナンス費用や人件費も工夫次第で削減可能です。
このように、1店舗目で得たノウハウを活かした取り組みは何事にも代えられない財産ですから、積極的に2店舗目の計画に活かすべきです。
また、基本的なランニングコストを削減することで、新しい客層を増やすためにアメニティやサービスを充実させるなど、ほかの部分にコストをかける選択肢も広がります。
従業員の確保と教育
サウナづくりと平行して、従業員の確保や人財育成計画を立てることも2店舗目づくりに欠かせない要素です。
近年はどの業界も人手不足の課題を抱えており、温浴業界も例外ではありません。
従業員の人数が不足することは必然ですので、サービスの質を少数で維持するための工夫を考えることになります。
従業員の確保は求人や賃金の設定も重要ですが、ソフトだけでなくハードの部分でも従業員が働きやすい空間をつくることも大切です。
例えば、動線設計の最適化: 清掃、補充作業、接客など各業務の動線が重ならないよう工夫したり、日常的に使う道具や清掃用品・消耗品を、取り出しやすい場所に配置し整備したり、クオリティが高い共有休憩スペース確保など従業員満足度を意識したバックヤードづくりも、業務効率が向上して人手不足解消につながります。
まとめ
2店舗目のサウナ出店は1店舗目の経営で分かっていることもありますが、トレンドやユーザーの思考など改めて考えるべき課題も多いです。
サウナ事業にとってのあるべき姿は、進化し続けている姿こそが温浴事業であり、設計や施工も同様に進化し続けています。
サウナブームが文化となった現在では、目新しい設備やサービスで競合と差別化することは前提であり、複数施設を運営し続けている温浴施設の基礎をベンチマークすることこそが大切なのだと思います。
実際のサウナづくりでは考えることが多岐にわたるため、温浴施設づくりの基礎をしっかり理解しているパートナーと組み、ユーザーに取って本当に魅力的な店舗をつくっていきましょう。
矢島建設工業は、多くのサウナづくりをサポートしてきたプロフェッショナルが、立地やコンセプトに合わせてアドバイスいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。



監修者情報

-
矢島建設工業株式会社 商環境事業部 事業部長
一級建築施工管理技士/監理技術者/サウナ・スパプロフェッショナル/DIYアドバイザー -
北海道生まれ。乃村工藝社、日商インターライフ、秀建などを経て2024年矢島建設工業に入社。
1985年から様々な商業施設の設計施工業務に携わり、3000件を超えるリアル店舗の設計・監修や施工・マネジメントを手掛ける。
近年はサウナ・温浴施設のプロジェクトに関わり、サウナ事業を学ぶため全国のサウナやフィンランド・ドイツ・エストニアにも渡って知見を広めている。
新事業のアドバイスを、ものづくりの目線から忌憚のない意見をする事がモットー。
第2期サウナ開業塾生
第1回Tehdään Sauna! Finland 修了
最新の投稿
- 2025年4月1日二世帯住宅2025年建築基準法改正で二世帯住宅はどう変わる?費用や工期など影響について解説
- 2025年3月31日リフォーム外壁カバー工法の失敗・後悔例|解決方法「モルタルカバー工法」も紹介
- 2025年3月7日平屋平屋が人気なのはなぜ?ブームの理由やトレンドの間取りの傾向を解説
- 2025年2月27日注文住宅ハウスメーカーと工務店の違いは?価格差だけでなくコストパフォーマンスを比較しよう